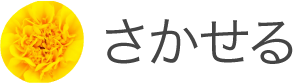以前、子ども達の休校期間中の不安解消を目的に開催した、PTA主催の「新1年生zoom交流会」について、こちらで紹介させていただきました。※その時の、開催詳細(プロセス・アンケート結果等)についてはこちらをご覧ください。
実は、交流会後校長先生から「PTAのようにスピード感をもってやることもとても大切だと思います。」とのご連絡をいただき、その後なんと子ども達の学校では、学校主体で全学年クラス毎でのオンライン活動が導入されました!
実施に至ったタイミングが、緊急事態宣言解除直前だったため、実現したのは1度だけでしたが、子ども達はとても楽しそうに、そして嬉しそうに、担任の先生や同級生とzoom越しに会話をしていました(^^)
前回、「アンケート結果をエビデンスに、学校や先生達のオンラインへの抵抗感を減らし、コミュニケーション手段としての信頼を得られれば、多少なりとも学校現場への導入の後押しになるのでは」と書きましたが、それが本当に実現できて、とても嬉しく思っています。
東京都では感染者数が増加傾向にあり、日本全体で見ても、いつまた登校できなくなる日が来るとも限りません。
前回のブログ公開後、実施に際しての様々なお問い合わせ等を各方面からいただきましたので、こちらにまとめさせていただきます。
オンラインはあくまでツールですが、非常事態時のソリューションには十分なり得ますし、非常時でなくとも、今後学校現場では必須のコミュニケーションツールになるに違いありません。様々な状況に備え、前回のブログと併せて、下記も参考にしていただけますと幸いです。
ご質問等ございましたら、facebookか下記コメント欄にお願いいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q.各家庭のネット環境等については、調査はしましたか?また、ネット環境の無い家庭に何か対応はしましたか?
→A.在籍する家庭の個別のネット環境については調べていません。ただ、家庭によるネット環境の差については、日頃の学校とのやり取りの中で学校からの配信メールを受け取れない家庭がないことを把握していたのと、総務省のデータ(平成 29 年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査 P.65参照)を根拠として判断しました。子どもの学校は、首都圏の1000人規模の小学校なので、総務省のデータより、更に普及していることを前提として考えました。
ですので、当事例の場合は”参加できなかった=ネット環境が整っていない”とはみなしていません。また、PTAのHPに交流会の詳細を掲載した際に、あくまで”参加は任意”であることと、wifi環境が整っていないと通信料がかかる可能性があることも明記し、問い合わせの受け皿も用意しました。その上で、特に参加できないことへの問い合わせ等はなかったので、”参加できなかった=参加しなかった”と判断しています。ただもちろん、地域によっては各家庭のネット環境に差のある可能性もありますので、その場合は何かしらの対応は必要だと思います。この平等性の担保については様々ご意見あるかと思いますが、”PTA主催”だからこそ、”学校主催”ではないからこそ、踏み出せた一歩だと思っています。
Q.先生方の休日活動について、どう思いますか?
→A.保護者の参加のしやすさを優先して日曜日開催としましたが、日曜日となると担任の先生に休日勤務を強いることになる為、担任の先生の参加は叶いませんでした。ただ、せめて校長先生から子ども達にメッセージが欲しい旨お願いしたところ、校長先生は休日にも関わらず、ご自宅から参加してくださいました。
その結果、「校長先生のお話が聞けてよかった:52.8%」「担任の先生のお話も聞きたかった:76.4%」というアンケート結果も出ていますので、校長先生が子ども達と保護者に向けて、顔を見せて話してくださったのは、よかったと思っています。もちろん、担任の先生が参加してくださったら尚更よかったのですが、先生方のプライベート時間を割いてまで参加していただこうとは思いませんでした。
Q.交流会当日は、運営の為のPTA役員は何人必要ですか?
→A.当事例の場合は、1クラスの交流会に司会進行として役員が1名参加しました。ただ、想定以上にたくさんの子ども達が参加してくれたため、司会一人で出欠確認や顔と名前のチェックは正直大変でした(^^;) 可能であれば、司会者1名+進行サポートが1名いると、色々な意味でスムーズだと思います。
Q.子ども達は、緊張して話せなかったりしませんでしたか?
→1年生は自己紹介など照れてしまってうまく話せない子もいましたが、そういう時は保護者の方に助けてもらいました。何しろ、子ども達が安心して楽しく参加することが大切ですから(^^)。また、得意なことを披露してもらったり、司会者が質問を用意したり、子ども達が自ら話してくれそうなネタを準備しておくのもいいと思います。
その他工夫したこと
・司会を務める役員はスマホから参加し、PCのバーチャル背景をその時の学校の写真に設定して、交流会のタイトル看板として使用しました。そうすることで、本来であれば登下校時に見ることのできる満開のつつじ越しの校舎を、子ども達にも見せてあげることができました。
・敢えて、ミュート機能は使いませんでした。子ども達みんなが「○○ちゃんがいる!」とか「○○がうつってる!」と口々に言ってザワザワしている方が、教室のリアルな雰囲気に近づけるかと思い。。もちろん、自己紹介の時には「お友達が話しているときは、静かにしようね」と声をかけ、自分が話さなければ静かになる、ということも多少なりとも体感することができたと思います。
・双子の在籍クラスを確認し、交流会の実施時間が被らないように調整をしました。これは、複数の学年で開催するときにも必要な留意点だと思います。各家庭にデバイスが複数あるかという点も重要ですが、特に単発の交流会であれば、低学年児は保護者と一緒に参加する方が、安心感もあっておしゃべりも弾んだように思います。
・とにかく”入り間違い””入りそびれ”がないように準備をしました。”入り間違い”については、zoomのURLの配信をクラス毎に分けて行うことで、自分の子どものクラスのURL以外知り得ないようにすることで防止しました。また、”入りそびれ”については、HPへのzoomアクセスマニュアル掲載、交流会前日のアクセス確認、ミーティングIDのURL埋め込みなど、できうる限りの対策を講じました。(詳細はこちらをご確認ください) とにかく当日、「入れなかった…」「みんなと会えなかった…」と悲しい気持ちになる子どもが現れないように、最大限気を付けました。おかげさまで、入れなかった家庭は1つもありませんでした。